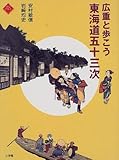|

[ 大型本 ]
|
TRANSIT(トランジット)4号~ハワイ特集 美しきハワイ~楽園のイブを探して (講談社MOOK)
【講談社】
発売日: 2009-03-05
参考価格: 1,600 円(税込)
販売価格: 1,600 円(税込)
Amazonポイント: 16 pt
( 在庫あり。 )
中古価格: 1,414円〜


|
|
カスタマー平均評価:  5 5
 写真がとってもきれい 写真がとってもきれい
とても美しい写真が目白押し
そして広くハワイに触れているところもおもしろいと思いました
 日本的でない感性豊かな雑誌 日本的でない感性豊かな雑誌
雑誌の写真の撮り方、対象物の選び方が、結構日本的ではないですね。
楽しんで、製作している編集体制がよく見えます。
それが、ハワイ好きの読者にダイレクトに響くのだと思います。
ところどころの「ウンチク」や人が入っていないハワイの自然を写し取った
見せ方。好きですね。
仕事柄ハワイには、多く行くのですが、
最近ハワイが、つまらないと思っていた自分にインパクトを与えた雑誌です。
想像力を画き立てる「1冊」です。
 美しきかなハワイ 美しきかなハワイ
イメージのハワイは、日本人が多く、ミーハー的な感じがしていて遠ざけていたきがします。しかし、そのイメージは見事に覆されました!海は青いんだとか、空は広いんだとか、当たり前の本来の自然の姿に改めて感動しました。自然を体感し、感動することすら忘れてしまっている毎日。旅に出たい!
 ハワイに今すぐ行きたい!! ハワイに今すぐ行きたい!!
今までの紹介誌とは違うハワイの良さをとてもうまく伝えている雑誌でした。
ハワイの目にも鮮やかな自然、ハワイの文化、どれもこれが体験できるなら今すぐハワイに行きたいと思わせるものでした。
写真がとてもきれいで深い群青色にはえる緑!!!
 買ってよかった雑誌NO1! 買ってよかった雑誌NO1!
NEUTRAL時代からのファンです。私は以前ハワイを訪れたことがあるのですが、TRANSITには私が見たハワイとはまったく似て非なるものが描かれていました。しかしそれはまぎれも無くハワイで、私が見たものよりもっと深い濃いハワイでした。TRANSITには毎回新しい風景をみせてもらっています。写真のクオリティーは旅雑誌というジャンルに限らず、その他どんな雑誌のなかでも一番であると思います。このクオリティーでこの値段。読んで損は無い一冊です。
|
|

[ 単行本(ソフトカバー) ]
|
悩んだときは山に行け! 女子のための登山入門
・鈴木 みき
【平凡社】
発売日: 2009-05-26
参考価格: 1,260 円(税込)
販売価格: 1,260 円(税込)
Amazonポイント: 12 pt
( 在庫あり。 )

|
・鈴木 みき
|
カスタマー平均評価:  4 4
 マンガとしては・・・ マンガとしては・・・
著者の「山が好きだ」という気持ちはとてもよく伝わってきました。でもマンガとしては、山登り、もしくは著者ご本人に、ものすごく興味がある人じゃないと、単調な感じがしました。著者と同じくらい「山が好き」な人にオススメです。
 山登りを始めたくて買いました 山登りを始めたくて買いました
山に関する情報だけでなく、本人の今までのバイト経験なども描いてあります。そこはなかなか面白くて笑える場面もありました。全部がイラスト&マンガなので、山登りに必要な物とか、気をつけるべきこととかの部分は、イラストと文字が小さくてごちゃごちゃしてます。どっち向きに読むの? と、迷うところもあって、ちょっと見づらかったです。でも入門書としては悪くないと思います。
 悩んだときは、この本をめくれ! 悩んだときは、この本をめくれ!
「悩んでいる」ときに、なぜ「山」に行くのか?
そんなこと、よく考えずに、
なんとなく手にしたら、、、おもしろかった。
山の魅力が、これでもか、これでもか、
と描かれている。
けっこう真面目なハウツー本でもある。
でも、いちばん面白いのは、
この著者かもしれない。
悩んだときに、山へ行くのもいいだろう。
でも、この本よんだら、
そんなに悩んでなくてもいいのかな、
と思えるような気がする。
著者自身が、いやしのオーラを出している、
そんな気がした読後感です。
 面白い!!女の子じゃないけど、ためになった。 面白い!!女の子じゃないけど、ためになった。
歳のせいだろうか。最近どうも「登山」といふものに興味が芽生えつつある。そんな折にこの本と出会えた。
幼少の頃から運動音痴を自認し、24歳で初めて山と出会ったという著者が、「バレーボールを顔面で受けるくらいの運動神経を基準に描いてます」というから、初心者には安心だ。
具体的にはどのようなノウハウが詰まっているのか。以下、本書の帯から抜粋。
「まずは何も買わなくてもOK!買うならこの3つ」
「お母さんは意外と山道具を持っているぞ」
「水筒はペットボトルでもいい」
「夏でもカイロは持って行け」
「まずは標高差MAX500メートルまで」
「お風呂に入らずに体をきれいにするには?」
「低山・縦走・温泉 厳選おすすめコース」
「おじさんにナンパされない方法」 ←げっ(引用者)
「山ではかっこよく見える男子も街では…」 ←げっ?(引用者)
上記以外にも、例えば山小屋について詳しく描かれているのも個人的にはありがたい。山小屋という存在は、未経験者にはよく分からない近寄りがたいものに映る。著者は山小屋の住み込みバイトの経験を踏まえ、利用側・提供側双方の目線から描いているから間違いないだろう。
「女の子のための登山入門」なのだそうだが、おじさんである私にも充分に役立ち、しかも楽しめた。面白いキャラと感性。女の子の読者だったなら、ノウハウを得るだけでなく、著者のその人となりや経歴にも共感するのではないだろうか。
しかしカラーページが無いのは惜しい。ここは次作に期待したい。
|
|

[ 単行本(ソフトカバー) ]
|
入門講座 2万5000分の1地図の読み方 (Be‐pal books)
・平塚 晶人
【小学館】
発売日: 1998-10
参考価格: 1,680 円(税込)
販売価格: 1,680 円(税込)
Amazonポイント: 16 pt
( 在庫あり。 )
中古価格: 1,102円〜


|
・平塚 晶人
|
カスタマー平均評価:  5 5
 読み物としては面白いが 読み物としては面白いが
25000/1の地形図を持って山に入るのは当然として、歩きながら頻繁に地図を確認するのは事実上困難だ。ルートファインディングでの地図とコンパスは、現在位置が正確に分かっていないと役に立たない。現在の位置を確認するのは標識の有る所が一番だが、そう都合良くは行かない。目印になる物、位置を特定できるもの(目立った地形や樹木)が有る場合はそれによって現在地を知ることができるが、初めての山で地形図だけで現在地を言い当てるのはほとんど無理だろうと思う。高度計などの助けが無ければ難しいと思う。初めての山で、薮で周りが何も見えない道、霧で目標になるピークや稜線が見えない時、実際には思ったようには行かない事が多いと思うのだが・・・。
知っている山を地図と照らし合わせて地形を思い描くのは簡単だから、筆者も現場で地図を見ろとしつこく言っているのだろうが。
筆者の地図読みの技術解説は的確で、とても良いのだが、仮にこの本のテクニックを総て覚えたとしても、読めない地形が幾らでも有る事をもう少し正直に書いてあれば、と思う。
GPSは今や絶大な威力を発揮するし、下手な地図読みよりは数段当てになる。そして、25000/1の登山道が実際と違っていたりする場合でも、新しい登山地図では指摘されている事も多く、普通に、普通の山に登る人には登山地図とコースガイドは地形図よりも有用な場合も多々ある、と思うのだが・・・素人の勘違いか?
 読図のバイブルです。 読図のバイブルです。
著者の豊富な経験と、山と読図を愛する熱意の賜物です。
本体と地図帳の組み合わせによる読図演習が面白くて引き込まれます。
地図が段々立体に見えてくるほど。
方向音痴の私でもこれを読んで、地図と磁石で随分と症状が緩和されてきました。
ただのノウハウ本の域を超える、バイブルと呼んでもいい、完成度の高い本です。
 地図を愛するすべての人へ 地図を愛するすべての人へ
本書の優れているところは、なんといっても、豊富な演習問題がついていることだろう。これだけで、星五つ分の価値がある。この手の本は、解説一辺倒になりがちだが、ちゃんと読者に問題を解かせる形式にした意義は大きい。地図に興味を持つ人は、ぜひ本書の問題集に挑んでほしい。
本書にも、いろいろケチのつけどころはある。著者はあまりにも2万5千分の1地形図絶賛一辺倒であり、『エアリア』をはじめとする登山地図を軽視しすぎている。GPSについても、過小評価しすぎだろう。地図の読み方・コンパスワークの方法についても、ちょっと杓子定規にすぎるきらいがある。だが、本書に掲載された膨大な演習問題の価値は大きく、減点対象とするにあたらない。なお、本書の欠点をカバーするには、他の参考書も当たるほうがよい。
本書を手にする人は、すでに山歩きの経験があり、登山地図を使っている人がほとんどだろう。本書でしっかり机上訓練したあとは、実際に地図を持って山に繰り出したい。
 想像してみよう。 想像してみよう。
本書は地図を見る上での注意する事や、コンパスの使い方などを解説しています。
しかもただ字だけで解説するのではなく、問いに対して実際の地図を見ながら考えるという小問題集のようになってるので解りやすく、地図を見て頭の中に山の形を組み立てていく作業は楽しいです。
唯一困ったのが、地図に触れた事がほとんどなかったため『沢があります』『登山道があります』という前提に対して慣れるまで戸惑った事でしょうか。
自分は仕事の休憩中などに少しずつ読んでるんですがボリュームがあるので読み応えもあります。
ただやはりこれ一つに偏る事なく登山地図なども読めるよう勉強したいです。
 山を登る人なら是非とも買いましょう 山を登る人なら是非とも買いましょう
この本は 2 万 5000 分の 1 の地形図から地形などを読み取り、自分の現在位置、これから進むべき道を読み取るための本です。
この本のなかにも書かれていますが、登山用の地図では誤ったトレールを取ってしまうことがありますが、この本で机上トレーニングすれば 2 万 5000 分の 1 地形図を読むことで、そのような失敗が激減します。
実際の地形図の例と、実習用の地形図が別冊になっているので、机上トレーニングにも最適です。
後、やはりこの本にも書かれていますが、この本を読んだだけでは山の中で地形図を読むことができるようにはなりません。
実際にこの本に書かれている方法で、2 万 5000 分の 1 の地形図を持ち込み、頻繁に地図と実際の地形を見比べながら山の中を歩いてみてください。2 万 5000 分の 1 の地形図の情報量の多さが実感としてわかります。
でも実際の登山、ハイキングでは登山地図と 2 万 5000 分の 1 地形図を併用するのが現実的でしょう。2 万 5000 分の 1 地形図にはすべての登山道が載っているわけではありませんから。
|
|

[ 単行本 ]
|
これで身につく山歩き100の基本―入門から中級まで (るるぶDo!)
・大関 義明
【JTB】
発売日: 2004-06
参考価格: 1,260 円(税込)
販売価格: 1,260 円(税込)
Amazonポイント: 12 pt
( 在庫あり。 )
中古価格: 859円〜

|
・大関 義明
|
カスタマー平均評価:  5 5
 超初心者にとって必読です 超初心者にとって必読です
山歩きをはじめようとウェア類を買ってしまってからこの本に出会いました。
「レベルに合わせた装備の揃え方」(P.98以降)を読んでから、靴、ウェアを揃えても遅くはないと思います。
歩くときは「バテない歩き方のコツ」(P.116以降)を参考にするとよいでしょう。
ほかにも携帯電話の使用方法やトイレ(「キジ打ち」(男性)、「花摘み」(女性)とか言うそうです)という細かいポイントも詳しく書かれています。
ただ、「山と文学」(P.184)に「神々の山嶺」が載っていないことが残念でした。
 山歩きに自信が持てる本です 山歩きに自信が持てる本です
健康とひまつぶしと歩いた後のビール(!)のためにハイキングをはじめました。といっても、技術も体力もない自己流歩き方ゆえ、高尾山や陣馬山がせいぜい。ウェアだけは一人前なんですけど……。そこで見つけたのがこの本。驚いたのは、写真で細かく説明している×な歩き方が、すべて私にあてはまること。ナント…これなら、疲れるわけだわー、と反省&納得。山歩きの基本を頭に叩き込み、さっそく梅雨の合間を縫って三頭山にチャレンジしてきました!! ブナの緑の素晴らしかったこと。消耗しないで歩くコツと下りのテクニックなど、著者の解説するわかりやすい基本は、ホントに身につきますよ。なにより山歩きがこんなに楽しいものだったなんて。サークルとかスクールが苦手な自己流山歩き屋さんにぜったいおすすめです。
|
|

[ 単行本 ]
|
東京ディズニーリゾート便利帖
・堀井 憲一郎
【新潮社】
発売日: 2007-07
参考価格: 1,050 円(税込)
販売価格: 1,050 円(税込)
Amazonポイント: 10 pt
( 在庫あり。 )
中古価格: 879円〜

|
・堀井 憲一郎
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 コンビニ本かと思いきや コンビニ本かと思いきや
コンビニ本程度の本かと思って馬鹿にしていましたが、案外役に立つので驚きました。この著者は落語本ではまったくダメですがこの手のデータ集積には力を発揮するようです。ま、あってもなくても構わない本ではありますが。
 3もだして!! 3もだして!!
これはすごい
前までのガイドブックは写真がいっぱいで
「夢にかかろうよ!」的な感じでしたが
「このアトラクションはここまで並ぶ」
などの
細かい情報が載っていたのでよかった
役に立ったのは
30ページの「モノレールの停車位置」
ですね
これは1回目だと全然わからないし
ここかぁ?って直感でのったら
めちゃくちゃ遠かったり・・・
いったときは電話予約のリロステショーが無かったので
スタートダッシュ覚悟で1人でも早くゲートに並ぶのを
心に刻んでいたときにこの本に出会いました
先月にはモンスターズインクもできましたし
2011年にはミッキーのフィルハーマジックも出るので
がんばってほしいです
 これはおもしろい! これはおもしろい!
TDLに持って行TDLに行こうかなと考えたときに読むにもよい本だと思います。著者のコメントがとても面白くて楽しく読むこともできましたし、図解されていて当日まで手放さないで勿論現地にももって行きました。これはお勧めです。
 新しいどの裏技本より役に立ちます 新しいどの裏技本より役に立ちます
最新版が待たれますが、基本の考え方をこの本で学べば応用できます。
データが古いと一蹴せず、混雑予想・待ち時間などはインターネットの
複数のサイトで検索できますので、新しいどの裏技本より役に立ちます。
裏技としてこの本と、最新の「ベストガイド」か「完全ガイド」の併用を
お勧めします。
 活字と数値と図面だけなのにスゴイね! 活字と数値と図面だけなのにスゴイね!
混雑時のまわり方、小さな子供が居る場合のまわり方、
時間別アトラクションの待ち時間、ファストパスの
最終発行時間など詳細なデータが満載!そして、
アトラクションやレストランの解説も詳細でうれしい!
写真も絵もないのに、こんなに満足な一冊が出来るとは
素晴らしいの一言!
データを活用して自分達のオリジナルルートを
考えるのも楽しいですよ。
そして何と言っても全トイレ一覧は凄かった…
施設ごとにトイレの個室の数を表示し、
並んではいけないトイレ、オススメトイレ(笑)を
教えてくれていました。これを知っておけば、
デートや子連れの際に、彼女や家族に尊敬されること間違いなし!です。
最新版の発売をお待ちしております!
|
|

[ 文庫 ]
|
深夜特急〈2〉マレー半島・シンガポール (新潮文庫)
・沢木 耕太郎
【新潮社】
発売日: 1994-03
参考価格: 420 円(税込)
販売価格: 420 円(税込)
( 在庫あり。 )
中古価格: 1円〜

|
・沢木 耕太郎
|
カスタマー平均評価:  4 4
 旅は人と出会うために行く 旅は人と出会うために行く
オリジナルは1968年5月リリースの『深夜特急 第一便』。本書はその後半部分を文庫化したもので、1994年3月25日リリース。文庫化の巻末には俳優高倉健氏との『死に場所を見つける』と題する1984年1月に掲載された対談が加えられている。この対談が本編と並ぶくらいに面白くて、文庫版をこの部分だけでも手にとって読む意味はある。
第二巻は『マレー半島・シンガポール』である。ぼくは10年ほど前にマレーシアを夏休みに一週間かけて車で縦断した経験があるので、特に興味深かった。ぼくの印象に最も残ったマレーシアはこの本にも乗り合いタクシーの部分で出てくるが『スピード狂』である。国民総スピード狂ではないかと思うほど、恐ろしいスピードでかなり古い車が文字通り飛び回っていた。バスを乗り合いタクシーが追い抜くシーンはそれと重なってしまって思わず頷いてしまった。
ここまで読んでみて思うのは、旅というのは名跡を見歩くのが楽しいのではなくて、そこにいる人たちと触れ合うことにこそ楽しさがあるのだな、ということだ。特にシンガポールのあたりでそう思った。そしてただただ羨ましい。ホントに羨ましい。そういう本である。
 マレー半島 香港・マカオとは一味違う旅の行方 マレー半島 香港・マカオとは一味違う旅の行方
沢木耕太郎の深夜特急シリーズは、バックパッカーの永遠の愛読書と同時に、今なお青春の書の代表のようなものでもあります。
全てを投げ捨てて、気ままな一人旅をしたい、と思ってもままならぬ現実があるわけで、本書を読む人は、沢木の行動に自分の夢を託しているのかもしれません。忙しく生活に追われる現代人にとって精神の開放につながる書籍でしょう。前作の香港・マカオの熱を帯びた文章と比較すれば、少し冷静な沢木を発見します。
アジアでも微妙に国民性が違い、それは、タイ、マレーシア、シンガポールと下るに従ってそれぞれの違いがはっきりしてきます。安宿を探すあまり、ペナンの娼館に泊まり続けるエピソードが興味をひきます。ヒモの生き方の大変さもうかがい知れました。沢木は冒険野郎ですが、このように冷静に人間の優しさ、悲しさを感じ取るという感性の豊かさが読者に心地よいのです。人との関わりを避けるように日本を離れながら、旅人は異国の旅先で人との関わりを持たざるを得ませんし、持つことを欲します。旅の醍醐味と真髄がここに出ているようです。
その昔、本書で描かれたペナン、クアラルンプール、シンガポールを旅行したことがあります。本書を読むとそれがいかに表面的なツアーだったかと思い起こしています。
沢木のような旅は、人々の間に入り込み、同じ食べ物を食べ、生活を一緒にすることで、深くその土地に根付き、その個性を浮かび上がらせます。それゆえ、同じ国でありながら全く違う印象を感じ取りました。
対談の高倉健との「死に場所を見つける」も面白く読みました。寡黙な人というイメージの高倉健が沢木と意気投合して様々な旅について語る話は本編とは別の意味で興味を惹きました。
 娼婦達と野郎ども。 娼婦達と野郎ども。
香港を出発して、マレー半島を下ってシンガポール向かう第2巻です。
なんといっても娼婦の館での件が面白すぎました(笑)。なんか陽気で和気あいあいとしてる
雰囲気が伝わってきて思わずニンマリ。娼婦にたかるヒモの若者達なんてギャグにしか思えな
いが世界は広いもんだ(笑)。
前回から亘って、同じアジア圏でも色々と差異もあり読んでて面白いですね。何か旅先で
出会う人々をみてると、やっぱ日本人って真面目なんだよなぁ?と感じます。まぁそのぶん
つまんないのかもしれないけどね。
人物描写もいいんだけど、食べ物の描写がいいな?。僕なんか普段食べたか食べないかわか
らないぐらい、食べることにこだわりも執着もない人だが、これ読んでると不思議なことに
無性に食い意地がはってきます(笑)。なんかどれもこれも美味しそうに思えてくる。
あと巻末についてる対談は高倉健さんとです。「死に場所を見つける」なんてヤバイぐらい
カッコいいタイトルだが、内容も渋くて勉強になりました。オススメです。
 曜日の感覚がなくなるなんてイイね 曜日の感覚がなくなるなんてイイね
私達はどこか別の世界に連れて行ってくれることを期待して本を読むことが多いです。この本は、ページをめくればいとも簡単に夜行列車の旅をしたり売春婦の館に泊まったりできてしまいます。
バンコクやシンガポールなどの都市は魅力が少なかったようですが、その分、多くの人とふれあい多くの人の親切を受けます。白人や黒人と違って黄色い肌のアジア人同士だとどっかで分かり合えるような気がします。
 マレー半島縦断鉄道の旅 マレー半島縦断鉄道の旅
前巻は香港・マカオの滞在型の旅でしたが、今回はマレー半島を移動しながらの旅行記となっています。
バンコクからスタートしてシンガポールまで途中いろんなところに立ち寄りながら長い時間をかけての旅となっています。
移動には鈍行の列車を使っており、現地の様子が伝わってきます。
いろんな場所を移動しながら、旅の技術が向上していっている様子が分かります。
特に面白かったのが、筆者が「そろそろ次の街へ移動する時期だ」と感じる瞬間です。
この感覚をマレー半島で見につけたことが、この後の旅をいい方向に導いたのではないかと思いました。
|
|

[ 単行本 ]
|
サービス発展途上国日本―“お客様は神様です”の勘違いが、日本を駄目にする
・奥谷 啓介
【オータパブリケイションズ】
発売日: 2009-05
参考価格: 1,575 円(税込)
販売価格: 1,575 円(税込)
Amazonポイント: 15 pt
( 在庫あり。 )
中古価格: 3,680円〜


|
・奥谷 啓介
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 The Plaza The Plaza
The plaza ホテリエ、ニュヨークに憧れる旅人が夢に描くアメリカを代表するグランドホテルである
良くも悪くもアメリカ社会の企業システムで生きた日本人が語る日本の常識は世界の常識ではなく改善せざるを得ない日本企業に我々にできるホスピタリティとは何だろう
 ホテルマンとしての幸せな人生 ホテルマンとしての幸せな人生
この本の最初の部分では、著者のホテルマン人生を、回想録として紹介していますが、
私にはここが最も面白かった。
スターウッドのスタッフとして、シンガポール、サイパン、そしてニューヨークとわたり、ホテルマンの仕事と生活を楽しむ。日本でホテルマンを続けて出世するようり、ずっとダイナミックで実り多い生き方だと思います。
どうしたら海外生活を満喫しながら、ホテルマンとして出世していくのか・・・。
キャリアアップのひとつの成功例として、とても面白いドキュメントでした。
もちろん、「お客様は神様ですの勘違い」がわが国をダメにしているという部分も
うなづくことばかりでしたが・・・。
 対等な人間として 対等な人間として
「いかに素晴らしいおもてなしをするか」
「いかに機知に富んだサービスをするか」
という内容のサービス本、過去に山ほど読んできました。
日本で実際にサービスをしてみるとわかる。特にホテルでは。
理想通りの、お客さまと近いフレンドリーなサービスをするのがいかに難しいか。
こちらが手を伸ばしても、お客さまは手を伸ばしてくれない。
なぜなら、彼らはどこかで「お金を払う方が立場が上」だと思っているから。
だから、そんなお客さまに、まずはサービス側の人間が“奴隷”ではなく、対等であることを認めさせなければならない。
言うことを聞くだけの奴隷ではなく、自分で考えて行動する“人間”だと。
そのために、たくさんのサービス本を読みました。
それが解決の糸口になったことも、決して少なくはない。
だけど、この本は、ちょっと異色。
サブタイトルの『お客様は神様ですの勘違いが日本を駄目にする』なんて、
実はサービスをする人たちの誰もが、こっそり思っていたことなんじゃないだろうか。
なぜここで、自分が我慢しなければならないのか?
どうして正しいことを言っているはずの自分が、折れなければならないのか?
毎日当たり前に繰り返している、たくさんの理不尽。
それらを、実に痛快に、バッサリと解決している欧米のスタイル。
サービスパーソンであることを、誇りに思いたい。
そんな人に、ぜひ読んで欲しい1冊でした。
 読み応えあります。 読み応えあります。
サブプライムローンに端を発した世界同時不況以降の日本では、
アメリカに学ぶものなど何もない、という風潮になっています。
しかし、オバマ大統領選で見た、
強いリーダーを待望し、それに従うアメリカの国民性を見て、
日本はリーダー不在で心細い国だとわたしは感じました。
リーダーをリスペクトし、それに素直に従うのは、
「いつか自分もあのようなリーダーになろう」と夢を抱くからだと著者は言います。
小学校低学年からそのような教育を受けるのだそうです。
尊敬できるリーダーと、信頼し合う仲間がいるNYザ・プラザで働くこと10年、
会社に行くことがいやな日は一度もなかったそうです。
それは、「スタッフの幸せをいちばんに考えるサービス業」のシステムが機能しているからに他ならないと。
この著者の本の特徴は、明晰で論理的で理解しやすいことにあります。
さらに、実践しやすい方法論を提示してくれています。
一流の世界のビジネスのノウハウを、気前よく教えてくれる一冊です。
 「日本の社会を変える一冊です。 「日本の社会を変える一冊です。
「日本の社会を変える一冊です。
この本を読むまで、社会の体制において、また企業の体質においても、日本が
アメリカに遅れているとは思っていませんでした。しかし、考えてみれば、先進
国一番の自殺大国、社会に蔓延する鬱病、多くの人が持つ強い離職願望、そして
大人社会の反映とも言える子どものいじめ等、こうした問題を抱える社会がまと
もなはずはなかったのです。今まで、うやむやに感じていたことをはっきりとこ
の本は指摘してくれています。そして、何が原因でこうなっているのか、どうし
たら人々が幸せになれるのかという解決策をも伝えてくれています。人々がこの
本に書かれていることに気がつけば世の中は確実に変わると思います。」
|
|
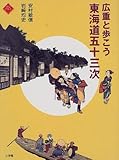
[ 単行本(ソフトカバー) ]
|
広重と歩こう東海道五十三次 (アートセレクション)
・安村 敏信 ・岩崎 均史
【小学館】
発売日: 2000-03
参考価格: 1,995 円(税込)
販売価格: 1,995 円(税込)
Amazonポイント: 19 pt
( 在庫あり。 )
中古価格: 1,944円〜


|
・安村 敏信
・岩崎 均史
|
カスタマー平均評価:  5 5
 絵の解説がよい。 絵の解説がよい。
丸子宿の丁子屋にて東海道五十三次の絵を見ていたら、何気なく見ていた絵がすばらしく、何か良い本はないかと思っていたら、丁子屋においてあった。その場は買わなかったが、家に帰りいてもたってもいられず、アマゾンで購入しました。やはりいいですね。
 街道てくてく旅を観ていたら… 街道てくてく旅を観ていたら…
先々月までは東海道のことは、あまり興味が無くて先月からNHKでこの番組が放映
されてから東海道の良さがわかってきました。
手元に東海道に関した資料が無く検索した結果、自分に合った本がこの本でした‥。
宿ごとの絵についての説明や解釈が書かれており、いい勉強材料になりました。
|
|

[ 文庫 ]
|
深夜特急〈3〉インド・ネパール (新潮文庫)
・沢木 耕太郎
【新潮社】
発売日: 1994-04
参考価格: 420 円(税込)
販売価格: 420 円(税込)
( 在庫あり。 )
中古価格: 1円〜

|
・沢木 耕太郎
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 どれもが『濃い』 どれもが『濃い』
オリジナルは1986年5月リリースの『深夜特急 第二便』。本書はその前半部分を文庫化したもので、1994年4月25日リリース。文庫化の巻末にはこの『3』で登場する此経啓助氏との1984年8月掲載の対談『十年の後に』が加えられている。
『深夜特急』自体の最初の部分は、この『3』のカトマンズの部分から始まっている。それだけ、この『3』に収められた部分が最もディープな場所だった、ということでもあるだろう。思い出したのは植草甚一氏の『カトマンズ・・・・』である。第8章『雨が私を眠らせる』では、文体まで変わり、手紙になり、そこで旅は停止したかのようになる。ベナレスでのドラマチックな日々やブッダガヤでの子供たちとの生活、どれもが『濃い』。
第一便と第二便の間が18年も開いたのは何故だろう。おそらくはこのインド・ネパール・パキスタンでの日々が何であったのかを、考えたのではないだろうか。ジム・ロジャーズのバイクと車での二度の世界一周の話にもシビれるが、沢木耕太郎のインドはもっとシビれる。
 沢木耕太郎 フィクションとノンフィクションの狭間 沢木耕太郎 フィクションとノンフィクションの狭間
多くのバックパッカー達を夢の世界へといざなってきた沢木耕太郎の『深夜特急』は何回読んでも彼の体験した世界へ惹きこまれていきます。本書の後半部分に書かれているインドのベナレスでの聖なるものと俗なるものの混沌とした日常にはあらためて驚きましたし、インド的なるものを追体験させてもらいました。
ガンジス河の沐浴所と死体焼場の隣接だけでなく、死体の扱いもまた日本人の死生観とは全く別の次元のものでした。このような筆者の体験がまた驚きとなって多くの若者をインドの旅へと誘っているのかもしれません。未知なる事柄に遭遇するたびに、旅そのものの魅力も感じるわけですが。
沢木耕太郎は、26歳の時に全てを投げ打って旅に出て、30代後半の時に本書(単行本)を世に出しました。実際、その間に10年以上の歳月が流れています。無名の作家も、この頃には有名な作家・沢木耕太郎として知られているわけで、若き旅人の無計画さと無鉄砲さをどこか冷静に見ている中年の作家がそこに存在しているのです。
彼の体験は当然全て実際上のものでしょうが、書かれている紀行文での彼の行動と考え方は、10数年という月日のフィルターを通して、消化され、旅のエッセンスを高い純度で再提示しているものと考えます。
それをフィクションというにはあまりにも早計です。旅の道中では、その坩堝に掘り込まれ流されている者にとって、その意味を知る余裕もありません。
人生を旅に例えますが、先の読めない旅の途中で、その時点を冷静に振り返るなんて作業は難しいに決まっています。だから、作家がしっかりと旅の意味を捉えた段階で文章化するのは「あり」でしょうし、その作業を経たからこそ、何十年と若者に支持されたわけで、ここに「深夜特急」の魅力が宿っていると思います。
 インドは今も変わっていないだろう インドは今も変わっていないだろう
私もインドを旅行したことがあります。日本の常識が通用しないことや人々の貧困に大変驚いたことを覚えています。
この本では駅や路上で生活している人やベナレスの死体焼場のことを取り上げていますが文章がどちらかというと冷静です。残念ながら1巻の「香港・マカオ編」のちょっとの事にも興奮して何でもやってやろうというワクワク感が減じてしまっているように思います。旅も佳境に入って、一日一日を現地の人たちとどうやって過ごすかということに重点が置かれているので仕方のないことかもわかりませんが・・。
 Deep Deep
とにかく深いインド・ネパール編。第八章の「雨が私を眠らせる」は手紙という表現上も
あわせて本当に淡々と描かれているが、それがまたアンニュイな気持ちにさせて、じめじめ
した気候を想像すると自分がとけていきそうな気がする。
第九章の「死の匂い」の死体焼き場をポツンと眺めてる著者を想像してると、気が滅入るが
そこの描写にあるように不思議な恍惚感が湧いてくる。
インドって国は不思議な国だとは思っていたが、何かこれを気に勉強してみたくなるような
もしくは行って見たくなるような変な気持ちになりました。
それにしても貧困に苦しむ子供たちの姿には胸が痛くなるが、本当にちょっとしたきっかけで
みせてくれる笑顔などというシーンでは心が温まるね。。。
あとラストの対談ではブッダガヤで出会った此経(これつね)さんと懐かしい回想などをして
ましたが、興味深く読めて面白かったです。
 インドの様子が分かります インドの様子が分かります
カルカッタ/ブッダガヤ/カトマンズ/ベナレス/デリーと転々としながらいろんな経験をしている様子が分かります。
筆者が旅行をしている時代のインド/ネパールの状況も分かります。
現在の状況と比較してみたくなりました。
前2巻と比較して、重たい内容も多くなっており、筆者が旅に慣れて現地のいろんな状況を感じ取ることができるようになっていると感じました。
|
|

[ 文庫 ]
|
深夜特急〈5〉トルコ・ギリシャ・地中海 (新潮文庫)
・沢木 耕太郎
【新潮社】
発売日: 1994-05
参考価格: 460 円(税込)
販売価格: 460 円(税込)
( 在庫あり。 )
中古価格: 1円〜

|
・沢木 耕太郎
|
カスタマー平均評価:  5 5
 予定を立てないということ 予定を立てないということ
自分もこのような旅をしてみたいと憧れます。「金」「時間」「英語力」「好奇心」「若さ」「決断力」考えてみればどれも今の自分には不足しているのでせめてこの本を読んで遠いトルコやギリシアに連れて行ってもらっています。
この本に書かれていることが本当ならば、著者は明日のことさえ考えずに旅を続けています。現在の日本に住んでいると、できるだけ先のことも予定が立たないと不安を覚える癖が付いてしまっています。果ては年金の心配までする始末です。本当はこの本に書いてあるように明日のことなんてわからない。道をぶらぶら歩いていると誰かから声をかけられあとはなるようにしかならない。この本の底流にはそのような思想があってその魅力で5巻まで読み続けることができました。6巻では、どのように旅を終えるのか楽しみです。
 飛光飛光 飛光飛光
オリジナルは1992年10月リリースの『深夜特急 第三便』。本書はその前半部分を文庫化したもので、1994年6月1日リリース。文庫化の巻末には高田宏氏との1992年10月掲載の対談『旅を生き、旅を書く』が加えられている。
実際に旅をしたのは26才、この第三便のリリースはその17年後の43才の時と言うことで、第二便からも6年が経過している。その意味でいささか『連続性』が薄れるのは感じるが、旅自体の魅力は減少しない。この『5』でついにアジアを離れ、ヨーロッパに入る。印象的なシーンが数多く登場する。そして歴史的建造物よりも、その土地の人に旅の魅力を感じる視点に共感を覚える。
ここに来て多くのデジャ・ヴを体験し、ゴールを意識するようになっている心理的な変化を語りはじめる。最終巻でこの気持ちがどうなっていくのか、が最も興味あるところかもしれない。
個人的に一番印象に残ったのは熊を使ったイスタンブールでの恐喝のシーン。絶対に日本にはいない。
 旅を内省的に少しずつ総括し始めた沢木耕太郎 旅を内省的に少しずつ総括し始めた沢木耕太郎
巻末の高田宏さんと筆者の対談でも語られていますが、26歳の時に旅をして本書を書いたのが、その17年後ということです。エピソードは全て青年期のものですが、書き手の感性は壮年に突入しているわけで、そこのギャップが作品のトーンに微妙に影響を及ぼしています。
旅の始めに遭遇した香港やマカオでの熱を帯びた行動と感覚が少し穏やかになっています。数か月の旅の間に、異国での生活が慣れてきたという説明だけでは収まりのつかない変化だと感じました。歳月が経つにつれ、本来強烈だった印象も少し客観的に眺めることができますので、その要素も本書には含まれているのでしょう。
66ページに筆者の壮行会を建築家の磯崎新と彫刻家の宮脇愛子夫妻が催したと書かれています。この二人との交友も気になりますが、それ以上は書かれていませんでした。その愛子夫人から頼まれたトルコにいるゲンチャイさんへの届け物のシーンは、この旅の中でも異色であり、そこには目的がありました。放浪の旅もまた目的を帯びることがあるのです。
そのあたりから他者との係わりの記述が少しずつ増えています。
アメリカでの生活をおいて、ギリシャのスパルタへ移ってきた老人も人との関わりを求めているようでした。地中海のフェリー・ポセイドン号での亜麻色の髪の女性もまた孤独から逃れるように筆者との関わりを持とうとしています。夢か現かでの会話も人生を旅に置き換えた場合、象徴的なやり取りだと受け取りました。李賀の「飛光飛光 勧爾一杯酒」の言葉にも過ぎゆく時への惜別の情があるように感じました。
旅の終え方に少しずつ話が向かっていますが、人生の終着と同様ならば、旅の終わりは誰にも分からないと考えますが・・・。
 旅と人生は似ている 旅と人生は似ている
旅にも幼年期、青年期、壮年期、老年期とあり、この巻では壮年期にあたる部分を描いている
確かにエネルギッシュに前へ、前へというよりは、何か心の隙間を埋めるように、それを
求めて前へ進んでいる印象を受けました。
個人的にはトルコ編はほのぼのとしていていいなぁ?と思います。香港のスターフェリーも
いいですが、こちらのアジアとヨーロッパを往復するフェリーは本当に羨ましいなと、、、
朝起きて、朝食を食べ、散歩してから食料を買いフェリーで風に吹かれぼーっとして、また
帰ってくる、たったそれだけの事がものすごく贅沢に思えてくる。
ギリシャ編では、スパルタの廃墟で出会った老人の件が感慨深いですね。年をとって好奇心
が磨耗しても人とだけは関わりたいというのがやっぱり素直な所なんだろうなぁ、、、
散歩してたらいきなりバースデーパーティーに誘われる件も、読んでて癒されます。やっぱ
人と人との繋がりはいいなと。
地中海からの手紙の章では、今までの旅の事をなかば自棄になって顧みてたりしますが、ほ
んと人生の壮年期と同じですよね(笑)。
最後にいったい何を得るのか、次の巻が楽しみです。
 ヨーロッパへの旅 ヨーロッパへの旅
アジアからヨーロッパへと移動して行きます。
トルコとギリシャの旅ですが、アジアからヨーロッパへと街のようすが変わっていくのが分かります。
長旅で慣れてきたのか、現地の人たちとの触れ合いが多くなってきているように感じました。
この巻では特にトルコからギリシャへの国境を越える部分が面白かったです。
|
|
















 5
5 写真がとってもきれい
写真がとってもきれい
 マンガとしては・・・
マンガとしては・・・


 4.5
4.5